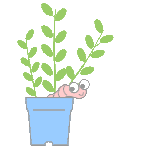 |
第15話 : エッセイ
須賀敦子をめぐって
第一章
昨年の中頃、H氏と連れ立って大先輩のI 氏を病院に見舞った帰りみち、駅近くの店にとび込んで生ビールで喉をうるおすことにした。H氏は二歳年上の温厚な先輩で、週のうち、草木の手入れをしながら別荘で数日を過ごすという生活をもう何年も続けていらっしゃる。次々と咲くバラを愛で、さまざまな野菜の新鮮な味を楽しみ、時にはバーベキューに舌鼓を打つH氏だが、良いことづくめというわけにはいかず、夏草や台風や害虫には相当悩まされているご様子。ともあれ、れっきとした晴耕雨読型仙人である。
現役時代は同じ社宅で暮らした時期もあったが、多忙な商社マンのこととて、ゆっくり雑談することもあまりなかった。ただ、家族ぐるみで知己になれたことは大きく、今も親しくしてもらっている一因となっている。そんなわけだから、H氏が無類の読書家であることに私が気付いたのは、近頃になってからと言っても大袈裟ではない。で、そんなロス(!?)を取り戻そうとするかの様に、口角泡を飛ばしつつ、私は下手な文学談義をおっぱじめるのである。
そのうち、ひとしきり作家と作品の品定めみたいなことを二人でしたころ、二杯目のジョッキを手にしたH氏は、「イタリア人と結婚したあの女流作家知ってる? 関西出身で、もう亡くなったけれど・・・。えーっと、名前は・・・そう、スガ・アツコ、須賀敦子っていうんだけど」と遠くを見るような目付きで言った。彼女の作品には私の感性に通ずるものがあるように思う、というのである。しかし、私には、まるで未知の名前であったので、この名を心に深く刻み、いささかの恥ずかしさとくやしさと感謝と期待の入り交じった感情のままに帰宅した。
第二章
なるほど、H氏は慧眼の士である。 − その後私は須賀敦子の『遠い朝の本たち』(筑摩書房)、『地図のない道』(新潮社)、『コルシア書店の仲間たち』(文芸春秋)をポツリポツリとながら読了し、今は『ミラノ 霧の風景』(白水社)を読んでいるが、H氏の言葉通り、作者の旺盛な好奇心・感受性・美しく磨かれた文章・思索のあと・論理などがしみじみと伝わってくるのを覚える。うなずいてばかりいる。波長が合う。私のタイプである。
≪葦の中の声≫と題されたエッセイにはこんな文章がある:
朝、家を出るとき、行ってまいります、今日、空襲で死ななかったら、夕方に会おうね、
と挨拶して、母が青ざめたのに笑いころげるほど、死は私たちの感覚から遠かった。
別のところでは、彼女は好きだったリンドバーグ夫人の『海からの贈物』から、以下の文を引用している:
我々が一人でいる時というのは、我々の一生のうちで極めて重要な役割を果たす
ものなのである。或る種の力は、我々が一人でいる時だけにしか湧いてこないもので
あって、芸術家は創造するために、文筆家は考えを練るために、音楽家は作曲
するために、そして聖者は祈るために一人にならなければならない。
須賀敦子(1929-1998)は兵庫県に生まれ、パリ、ローマに留学したのち、ミラノでイタリア人と結婚(1961年)。ミラノなどに住んで、川端、谷崎など日本文学の名作を数多くイタリア語に翻訳する。夫“ペッピーノ”と1967年に死別。1971年にイタリアから帰国後、上智大学教授。1991年、デビュー作『ミラノ 霧の風景』で女流文学賞、講談社エッセイ賞。明るく、いたずら好きな人であったという。しかしその作品は静かで、随所で深い思索の跡を感じさせる。また、とりわけ孤独ということについて、多面的に思いをめぐらせ、凛として生きた人であった様に私には思える。
そんな中で、昨年11月になって、BS朝日から平成18年度文化庁芸術祭参加作品「イタリアへ・・・須賀敦子 静かなる魂の旅」が放映された。新聞広告には≪女優・原田知世の美しい朗読で綴る“テレビエッセイ”≫とも書かれていた。私はこの静かな心象風景を再放送で楽しむことが出来た。一方、今年つまり2007年が始まると、年明け早々から朝日新聞が「異才伝」なるコラムで4回にわたって須賀敦子を取り上げた。
かくて、文章を通じて想像していたミラノの風景が、時代のずれはあるにせよ、映像として私の中に入って来た。もしも須賀さんが今も存命で、80歳近くの目でコルシア書店の跡(現況)を見たらどう思うだろうか、と考えたりもした。しかしそれより、私には、須賀さんの肖像(写真)に初めてお目にかかれたのが大事だった。思っていたよりずっと丸顔で、生気にあふれ、生活力十分といった感じがした。
第三章
話はここから思わぬ方へ飛ぶ。今月になって、新聞に出ている映画広告多数の中に、「パフューム − ある人殺しの物語」を見て、私はアッと思った。ピーンとくるものがあった。そうだ、これは須賀敦子が『ミラノ 霧の風景』中の一話で触れている小説のことだ。じっさい、≪チェデルナのミラノ、私のミラノ≫の中で、彼女はこう書いている:
数年まえの夏、イタリアに滞在していたときに、「新聞小説の復活」というふれこみで日刊紙『コリエーレ・デラ・セーラ』の紙上をにぎわした、そのために私が毎日、早起きして新聞を買いに行くほど熱中して、友人たちにからかわれた小説があった。『香水』という題のその小説の主人公は、のちに稀代の香水づくりの名人となるのだが、(後略)
この偶然にひどく心を動かされた私は、おっとり刀で映画館へ走った。当分、この「秘密」は誰にも漏らさないぞと心に決めながら・・・。
映画は、力の入った、しかもエンターテインメントとしても十分に楽しめる、期待を裏切らないものであった。そして、私が昔みた映画「ブリキの太鼓」を連想したり、カフカの小説「変身」とも共通していると感じた裏には、原作者がドイツ人であることが関係していよう。つまり、私なりに解釈している≪北欧的なるもの≫が濃厚である。ま、この映画の驚くべき結末は言わないのがマナーというものであろう。なお、邦訳が文春文庫に入っていることも最近知った。
― H氏と飲んだビールが須賀敦子につながり、彼女を読んでいる間に新聞記事やテレビ作品がひょっこり浮上し、一方で彼女の作品が私を映画に結びつけてくれた。こうした因縁めいたものがやけに気になるのも、歳をとった証拠に違いないとは思う。がしかし、自分に忠実になって、ささやかな因縁ばなしを書き上げた今、私はサバサバとした良い気分になっている。
(2007/03/18)
| 2006/11/13 |
![]()
Last updated: 2007/6/25
